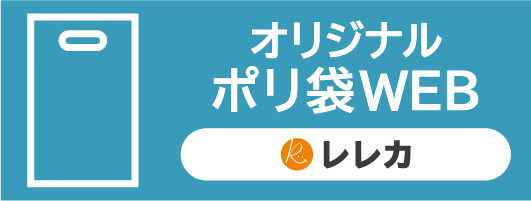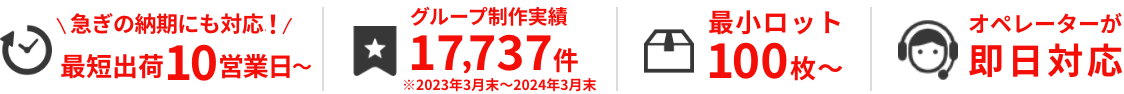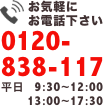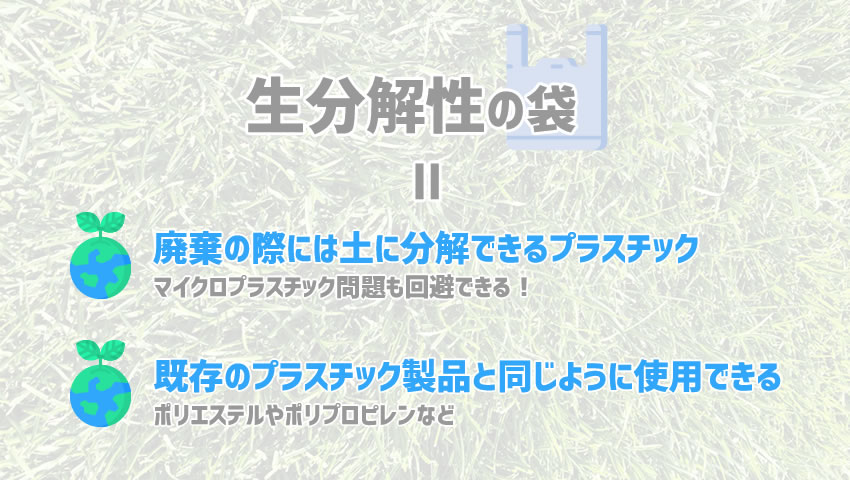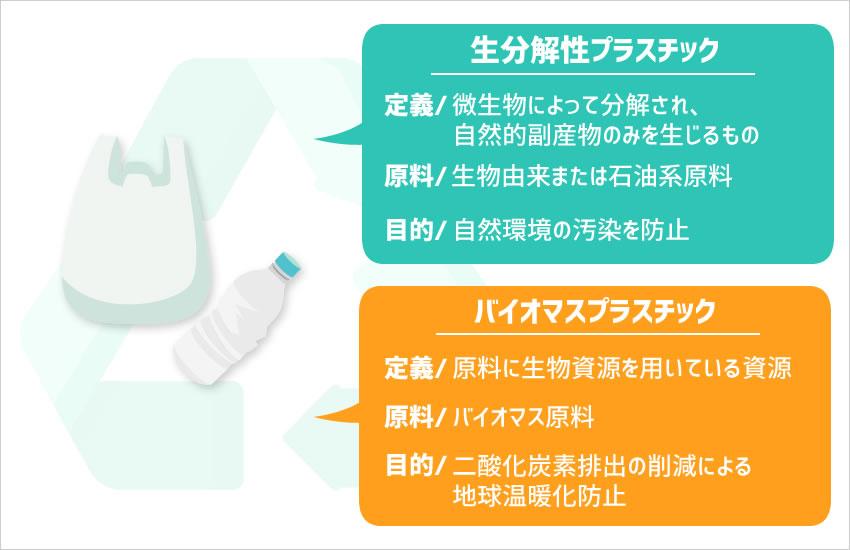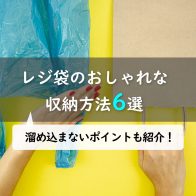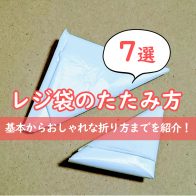- 2023/04/03
- レジ袋有料が義務化!?環境省が検討
- 2023/04/03
- 安くレジ袋に名入れをする方法 オリジナリティを出す方法も紹介
- 2023/04/03
- 進むレジ袋の有料化!スーパー毎に比較レジ袋の料金
- 2023/04/03
- レジ袋のおしゃれな収納方法6選|溜め込まないポイントも紹介!
- 2023/04/03
- レジ袋のたたみ方7選|基本からおしゃれな折り方までを紹介!
- 2023/04/03
- レジ袋のサイズ選びに困ったら! ピッタリなサイズを選ぶための3つのポイント
- 2023/04/03
- レジ袋への印刷方法と、人気の仕様をご紹介します!