- 2023/04/17
- ビニール袋の素材とは? ポリ袋との違い、見分け方についても解説
- 2023/04/17
- ポリ袋の厚さは、それぞれどう違う? 比較検証してみました!
- 2023/04/17
- ポリ袋カラー生地の作り方と注意点
- 2023/04/17
- ビニールの歴史
- 2023/04/17
- レジ袋のおしゃれな収納方法6選|溜め込まないポイントも紹介!
- 2023/04/17
- ポリ袋の印刷方法の種類と、その注意点をまとめました

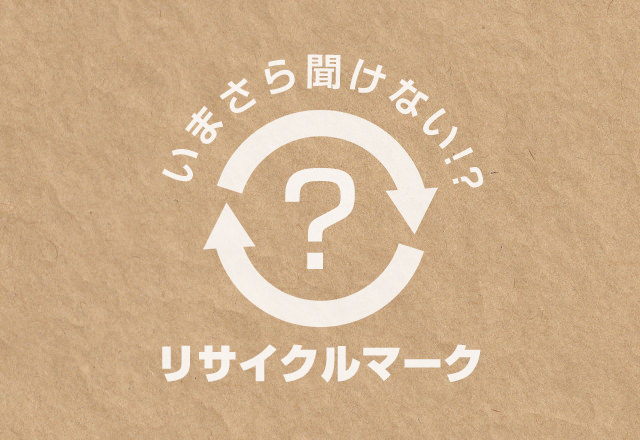
 皆さん、このようなマークを見たことはありますか?
左が「紙マーク」、右を「プラマーク」です。 紙マークは、弊社・レレカでも取り扱いのある紙袋をはじめとする、紙製品には必ず表示しなければならないマーク。
また、プラマークは、主にプラスチック製品に表示義務があるマークです。
レレカの商品ではポリ袋が該当します。 紙マーク、プラマーク以外にも、こういったマークがいくつかあります。
なかには、よく目にするものも。
皆さん、このようなマークを見たことはありますか?
左が「紙マーク」、右を「プラマーク」です。 紙マークは、弊社・レレカでも取り扱いのある紙袋をはじめとする、紙製品には必ず表示しなければならないマーク。
また、プラマークは、主にプラスチック製品に表示義務があるマークです。
レレカの商品ではポリ袋が該当します。 紙マーク、プラマーク以外にも、こういったマークがいくつかあります。
なかには、よく目にするものも。
| アルミ缶 |  | 飲料、酒類用のアルミ缶 |
|---|---|---|
| スチール缶 |  | 飲料・酒類用のスチール缶 |
| PETボトル |  | 飲料、酒類、特定調味料用のPETボトル |
| 紙製容器包装 |  | 飲料用紙パックでアルミ不使用のもの、および段ボール製容器包装以外。 |
| プラスチック製容器包装 |  | PETボトル以外のプラスチック製包装容器 |



 では、次の場合はどうなるのでしょうか?
では、次の場合はどうなるのでしょうか?